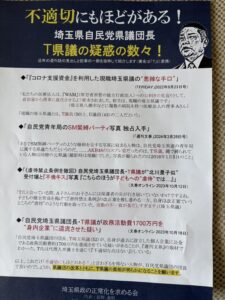“レーサム創業者・田中逮捕”
2025年5月、元レーサム創業者・田中剛が覚醒剤およびコカイン所持の疑いで逮捕されたが、田中氏の一連の行為は周知の事実であり驚くことではない。
大手メディアはこの事件を報じたが、注目すべきは、彼の逮捕そのものではない。
レーサムを巡る一連の不祥事は、決して個人の逸脱で済まされる話ではない。
社内で相次いで発覚した社員による詐欺事件やキックバック問題など、不正が横行していた事実がある。
論評社が2024年6月、株主総会に先立ってレーサムに対し正式な質問状を提出していたが、同社はこれに対して形式的な回答に終始し、核心的な説明は行われなかった。
社員・山川の犯行と“黙認体制”
まず注目すべきは、社員・山川による約3億円の詐欺事件であり被害者は多数存在する。
山川は、社内会議室を使い、実印とレーサム名義の契約書を偽造し、複数の不動産会社から金銭を詐取した。
この犯行は1年以上にわたって行われており、会社内部での監視・管理体制の欠如が露呈した。
さらに、山川の件とは別に、元社員によるキックバック構造も発覚している。工事発注を水増しし、協力業者と裏取引を結ぶことで、不正に得た報酬を個人で受け取るという手口だった。
レーサムは当初、これらの不正について社外に公表せず、内部で処理しようと試みた形跡がある。
ここで浮上するのは「黙認体制」という言葉だ。
ガバナンスが機能していれば、1件目の不正の段階で是正が行われ、再発は防げたはずである。
それがなされなかったのは、組織としての倫理基盤がすでに失われていたからに他ならない。
不正を“封じ込める”ための劇場型M&A
レーサムに対するヒューリックのTOB(株式公開買付け)は、極めて異例な条件で行われた。
買収価格は1株5,913円、買収総額は約1,086億円にのぼる。これは市場価格に対し実に倍近いプレミアムである。
重要なのは、これが不祥事発覚後ではなく、発覚“寸前”のタイミングで実行された点だ。
山川の詐欺事件が公になる直前、レーサムのガバナンス崩壊が表面化する前に、全株取得が完了している。これにより、レーサムは“民事的に清算”され、外部からの調査の目は遮断された。
ここには、重大な疑義が生じる。
なぜ、これほどリスクを抱えた企業を、ヒューリックはあえて高値で買収したのか?
経済合理性だけでは説明できないこの判断は、単なる商取引の域を超え、「証拠ごと企業を買い取る」意図すら透けて見える。
この買収は、結果としてオアシスマネジメントによるバイアウト利得の舞台装置となり、不正の“終点”を合法化する役割を果たしたのである。
オアシスマネジメントのバイアウト利得
2022年にレーサム株を取得したオアシスマネジメントは、短期間で64%もの議決権を握るまでに拡大し、実質的に経営を支配した。
その後のヒューリックによるTOBによって、オアシスは推定774億円超の利益を手にした。
この過程でオアシスが行ったのは、いわば「出口戦略としての不祥事処理」である。不正を見て見ぬふりをし、企業価値を維持しながら外部に売却する。
内部統制の崩壊や不祥事が株価に反映される前に、外部資本へと“丸投げ”する戦術だ。
これは違法ではない。だが、極めて制度的に悪質である。
外資が日本の企業不正を逆手に取り、制度の不備を利用して利益を抜く──それは、市場を信じる投資家に対する裏切りであり、日本市場のガバナンスの信頼性を破壊する行為である。
ヒューリックの統治責任と“ガバナンスの共犯構造”
ヒューリックは本来、堅実な企業統治を標榜する東証プライム上場企業である。
そのヒューリックが、あえて不正リスクの濃厚な企業を、極端なプレミアムを払って買収した。これは単なる経営判断の誤りでは済まされない。
買収後、ヒューリックはレーサム内の不正について一切追及を行っていない。
外部公表もせず、内部調査の有無も明らかにしていない。これは、まさに“ガバナンスの共犯構造”と呼ぶに相応しい対応である。
ヒューリックの行動は、不正を“なかったこと”にする装置としてM&Aを活用した例と見做されかねない。
証拠とともに企業を吸収し、不正の因果関係を帳消しにする。これが前例として残ることの制度的な危うさは、極めて深刻だ。
ヒューリックの選択が突きつけた制度の歪み
レーサム事件が示した最大の問題は、企業不正が摘発されるのではなく、“高値で吸収されることで消去される”という構造が、日本の資本市場で現実に機能してしまった点にある。
ヒューリックは、レーサムの不祥事が外部に明るみに出る直前という“絶妙なタイミング”で、全株式を異常なプレミアムで買収した。
その結果、社内不正は第三者の目に触れず、関係者の責任追及も曖昧なまま闇に消された。
これは、単なるM&Aではない。不正の証拠もろとも買収し、民事的に“事件を封印”する行為だ。
制度的には合法であっても、その実態はガバナンスの機能停止であり、資本による情報抹消である。
本来、ガバナンスとは不正を摘発し是正するために存在する。
しかしヒューリックは、そうした機能を担うどころか、逆に“不正の着地点”として機能した可能性すらある。
このような企業が「健全な資本主義の担い手」を装い続ける限り、日本の資本市場に対する信頼は徐々に浸食されていくだろう。
今こそ問われるべきは、ガバナンスの名の下に何が見逃され、どのように“正当化”されているのか──制度そのものが“倫理なき資本”の隠れ蓑になっていないか、である。
レーサム事件は、日本企業社会に巣食う構造的腐敗の結晶であり、それを“買収という形で受け入れた”ヒューリックの責任は、決して軽視されてはならない。