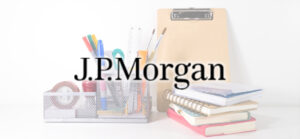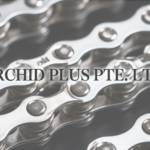伝統と資本構造に見る建設業界の一断面
企業概要
株式会社森組は1934年に創業された大阪本社の建設会社であり、90年近い歴史を持つ中堅ゼネコンである。
1949年に建設業法に基づく登録を受け、1963年には大阪証券取引所市場第二部に上場。その後、東京証券取引所の市場再編を経て、現在は東証スタンダード市場に上場している。
主な事業領域は以下の3つに区分される。
-
建設事業(建築・土木)
-
不動産事業(賃貸・仲介)
-
砕石事業(製造・販売)
現在は建設事業が収益の柱であり、2025年3月期時点で売上全体の約97.7%を占めている。
また、同社は旭化成ホームズ株式会社を筆頭株主(30.3%)とする関連会社であり、2022年より資本関係が再強化された。
過去には長谷工コーポレーションの関連会社であった歴史もあり、業界大手との資本的繋がりを軸にした経営体制を構築している点が特徴だ。
従業員数は328名(平均年齢44.5歳、平均年収722万円)と、比較的安定的な人材構成を維持しており、建設業界において一定のプレゼンスを有する企業である。
財務サマリー(第92期・2025年3月期)
| 指標 | 数値 | 前年比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 294.5億円 | +6.8%増 |
| 営業利益 | 10.8億円 | +0.9%増 |
| 経常利益 | 10.4億円 | +1.3%増 |
| 当期純利益 | 9.2億円 | +34.3%増 |
| 営業CF | ▲42.3億円 | 大幅悪化 |
| 現預金残高 | 44.7億円 | ▲53.3%減 |
| 自己資本比率 | 58.9% | +6.5pt上昇 |
収益は微増で安定しているものの、営業キャッシュフローの急減(前年比▲46.9億円)は極めて深刻である。
セグメント構造
■建設事業
売上:287.7億円(+6.9%)/セグメント利益:22.3億円(+10.2%)
公共:民間比率は43.5%:56.5%。特に建築工事の民間比率が88.1%に達しており、民間案件依存が高まっている。
■砕石事業
生瀬砕石所の譲渡が決定(2025年9月末予定)。セグメント損失が発生しており、構造的撤退フェーズにある。
■不動産事業
売上0.32億円、セグメント損失▲0.18億円。規模・収益性ともに極小で、名目的存在にとどまる。
以上より、実態としての収益構造は「建設偏重」であり、将来的なリスク分散策の欠如が課題として浮き彫りとなる。
キャッシュフローの崩壊
「利益は出るが金が消える」
最も重大な構造リスクは営業キャッシュフローの激変である。
-
営業CF:▲42.3億円(前期+6.8億円)
-
現預金残高:44.7億円 → 前年比で半減
-
キャッシュ減少の主因:売上債権の増加(+19.9億円)、消費税の未払/未収ズレ(+14.6億円)など
利益が増えているにもかかわらず、資金が消えるという構造は、営業実態と会計上利益の乖離を意味する。
とくに完成工事未収入金は153億円と総資産の60%超を占め、資金回収リスクは顕著。
これは、B/S上は健全でもC/Fは危機的という「粉飾でないが危うい企業」の典型症例である。
人的資本とESG
形式主義にとどまるか
-
管理職に占める女性割合:2.8%
-
男女賃金差:正社員ベースで28.1%
-
働き方改革指標(4週8閉所):76.9%実現(未達)
-
GHG削減目標:2030年に42%削減(SBT認定)
人的資本や環境配慮への取組は明記されているものの、実態としてはジェンダーギャップや労働慣行の改善余地が大きく、制度先行・実効性後回しの印象が拭えない。
資本政策とガバナンスの構造
-
筆頭株主:旭化成ホームズ株式会社(30.3%)
-
社外取締役:2名(うち1名は大阪ガス系)
-
ガバナンス構造:執行役員会主導・社長直轄
-
配当性向:49.8%(1株当たり配当:14円)
ガバナンスは機能しているように見えるが、キャッシュ崩壊への対応や構造改革のスピードは鈍く、取締役会が形式化している懸念がある。
実質的には親会社の意向が色濃く反映される経営構造といえる。
森組は「見かけ上の安定」に騙されていないか
第92期決算は、利益成長とキャッシュ崩壊が同時進行する「静かな危機」の兆候を示している。砕石事業の撤退、不動産事業の停滞、建設事業の民間偏重──これらはすべて、収益の未来が縮小方向にあることを示唆する。
財務的には自己資本比率が上昇し、配当も継続されているが、それはあくまで「粉飾されていないが錯覚的な健全性」であり、C/Fの赤信号が鳴り続けている限り、企業の実質的価値は毀損されつつある。
森組に今必要なのは、現場主義から資本効率主義への転換であり、「過去の慣習と安定志向」からの脱却である。収益の質と回収力を取り戻さない限り、この企業の未来に真のサステナビリティは訪れない。