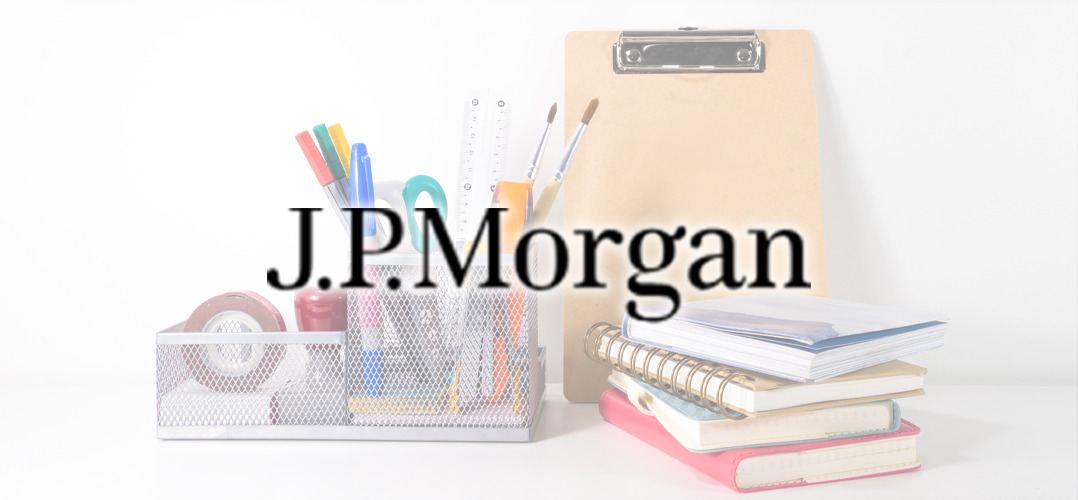
大塚商会に対する5.17%保有の構造と真意
2025年7月3日、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社を筆頭とするJPモルガン・グループ7社は、大塚商会(証券コード:4768)に対し、発行済株式総数の5.17%に相当する19,649,653株の保有を開示する大量保有報告書を関東財務局に提出した。
本報告は「特例対象株券等」に該当し、基本的には顧客資産や投資信託の運用に伴う純投資とされているが、その実態はより複雑かつ多層的である。
7社に分散された株式と担保構造
報告書によれば、JPモルガン・グループの保有株式は以下の7法人に分散されている。
| 保有者 | 株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| JPモルガン・アセット・マネジメント(日本) | 1,942,300 | 0.51% |
| J.P. Morgan Investment Management Inc.(米) | 2,011,600 | 0.53% |
| JPMorgan AM (Asia Pacific) Limited(香港) | 494,900 | 0.13% |
| JPモルガン証券株式会社(日本) | 12,196,621 | 3.21% |
| JPモルガン・セキュリティーズ plc(英国) | 317,228 | 0.08% |
| JPモルガン・セキュリティーズ LLC(米国) | 1,179,904 | 0.31% |
| JPモルガン・マンサール・マネジメント Ltd.(英国) | 1,507,100 | 0.40% |
最大保有者であるJPモルガン証券(日本)が全体の約3分の2(3.21%)を占めており、その他はアメリカ、イギリス、香港の関連法人に分散されている。
特筆すべきは、担保契約・消費貸借の存在である。報告書には、JPモルガン証券が英国法人との間で3,483,119株の貸付・1,967,634株の借入を行っていることが記載されており、同一グループ内での名義移動や空売り・裁定取引の布石となりうる取引形態が確認される。
保有目的の名目と実態のギャップ
各社とも「投資顧問業務の一環として顧客の資産運用上必要な範囲での純投資」あるいは「証券・銀行業務のための保有」と記載しているが、形式的な記載に終始しており、実際の保有目的は極めて流動的である。
特にJPモルガン証券(日本)およびセキュリティーズLLCは、保有株の一部を「プライムブローカレッジ契約」等で他機関投資家へ貸し出しており、名義上の保有と議決権の実効支配が乖離している可能性がある。また、短期売買やデリバティブ・ヘッジに用いられている可能性も排除できない。
閾値を超える“必要性”
報告書の提出は、保有割合が5%を超えた時点での法的義務によるものだが、そもそもなぜ5%超の水準にまで達したのかという背景に注目すべきである。
本件では、**7法人合算での5.17%**であり、実際には特定の単独法人が5%超を占めているわけではない。しかし、一定期間内に合計でこの水準に達してしまった背景には、
- 複数のファンドでの買付集中
- 機関投資家間の株券移動
- 裁定・貸借スキームの組成
などが複雑に絡み合っているとみられる。
加えて、大塚商会はオフィス機器・ITインフラ導入支援を中心とするBtoB系上場企業であり、ESGテーマやディフェンシブ資産としての位置づけから機関投資家による指数連動・セクター投資の対象となりやすいという点も背景として考えられる。
「実質的保有」と「ガバナンス上の透明性」の乖離
今回の大量保有報告は、一見すると形式的な外国人機関投資家の開示にすぎないように見えるが、実際には「名義上の保有」≠「実質的影響力」という現象が露呈している。
特に、複数の担保契約、消費貸借、機関投資家間の貸借契約が並行して記載されている点は、株主としてのガバナンス権限が実体として誰にあるのかを不明確にする構造的なリスクである。
大塚商会のような中核IT企業において、JPモルガンのような超大手外資系金融グループが5%超の資本を断片的に、流動的に保有することは、資本の“帳簿上の存在感”と実質的な関与のギャップを際立たせる結果となっている。
論評社としては、こうした「実質支配構造の透明性不全」に対して、
- 今後の議決権行使の履歴・開示
- プライムブローカレッジ等に関する外部開示
- 日本企業側からの持続的なエンゲージメント要求
などを中心に、形式的保有と実効支配の乖離という問題構造を継続して監視・分析していく所存である。

















