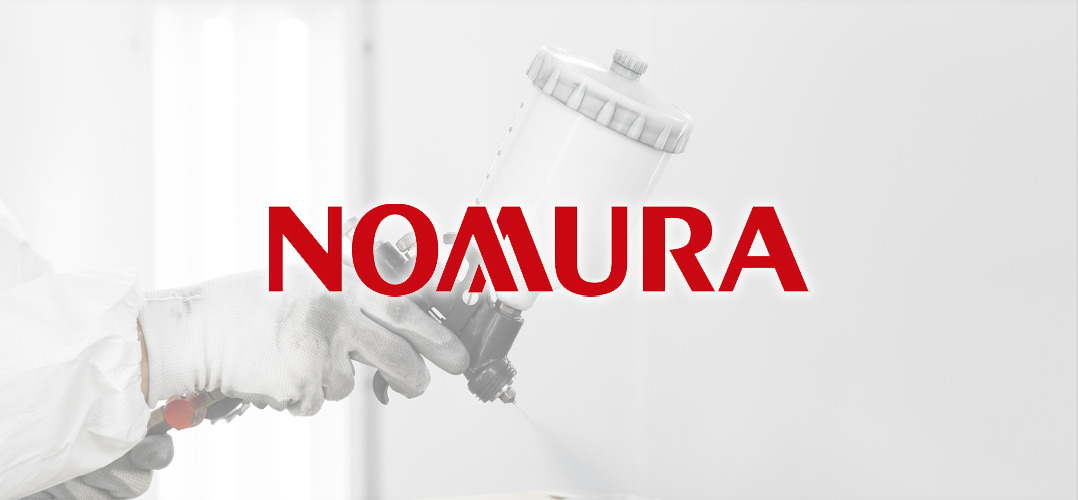
現物・貸借・信託を統合した日本型キャピタル・アーキテクチャの全容
2025年7月17日、野村證券株式会社を中心とする野村グループ3法人は、長瀬産業株式会社(証券コード:8012)の株式5.08%(5,586,518株)を共同保有している旨の変更報告書を関東財務局に提出した。
表面的には「証券業務」「信託運用」「商品在庫保有」などの名目で構成されているが、報告書の記載内容を精査すると、これは日本型証券コングロマリットによる三層構造的“戦略的資本操作”の典型である。
野村證券 × 野村インター × 野村アセマネの三位一体
報告書に記載された保有内訳は以下の通り
| 保有主体 | 保有株式数 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 1,347,474株 | 1.23% |
| 野村インターナショナルPLC(英) | 998,744株 | 0.91% |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 3,240,300株 | 2.95% |
| 合計 | 5,586,518株 | 5.08% |
-
野村證券: 国内証券部門によるマーケットメイク・引受業務および自己在庫管理
-
野村インター: 英国拠点を活用したクロスボーダー証券貸借と裁定取引
-
野村アセマネ: 投信・年金等による信託資産の中長期保有
という明確な役割分担がなされている。これは、現物保有、担保・貸借在庫、ファンド運用という“三位一体”の資本ポジショニングだ。
“控除株式”の存在が示す戦略的流動性供給
今回の報告書では、株式の保有構造に以下の記載がある。
-
野村證券は日本カストディ銀行に700,000株を担保差入
-
野村インターはノムラセキュリティーズ(米)から1,500株、他機関から約233万株を借入れ
-
野村アセマネはSG証券・バークレイズ証券へ合計17,600株を貸出し
特に注目すべきは、「引渡請求権等による控除株式」として1,332,841株が控除されている点である。
これは、共同保有者間での貸借契約を通じて、実質的な価格形成における影響力と市場流動性をコントロールする仕組みを構築していることを意味する。
「物言わぬ構造圧」による日本企業への接触法
報告書上は各社とも「証券業務の一環」「信託財産の運用目的」とし、提案行為の意図は否定されている。だが、実態として
-
株価水準:PBRは1倍割れが続き、資本効率改善圧力が高まる
-
自己株式:安定推移、積極的な還元策には至らず
-
財務:純資産比率は高水準で現預金も豊富
という条件を背景に、**“明示的アクティビズムは行わずとも、資本政策の方向性に「構造的圧力」をかけられる立場”**を野村グループは獲得している。
長瀬産業とは──商社×化学に強み、だが低PBRの割安銘柄
長瀬産業は化学専門商社として、以下の特徴を持つ:
-
売上:約8,000億円
-
セグメント:ケミカル、機能材料、医薬原薬、エレクトロニクス等
-
自己資本比率:約65%前後
-
株主構成:事業会社・金融機関・個人株主中心で、アクティビスト色は薄い
だが、2023年度以降のPBRは0.8倍前後と低迷しており、東証のPBR是正圧力を背景に、「静かな外圧」が資本政策に影響を与える余地は大きい。
日本型多機能証券グループによる“構造的プレゼンスの可視化”
本件報告は、「アクティビストではない」「物言わない機関投資家」の名を借りつつ、実際には
-
株式現物・貸借・信託を分散管理し、
-
資本政策の選択肢に“構造的影響”を及ぼし、
-
社内外の資本パワーバランスに“静かな揺さぶり”をかける
という高度に制度適合的な“資本のリアレンジ戦略”の一端を成している。
それは、日本の大企業にとって、単なる機関投資家ではない「構造を持った存在」として、今後も無視し得ぬ圧力となっていくだろう。

















