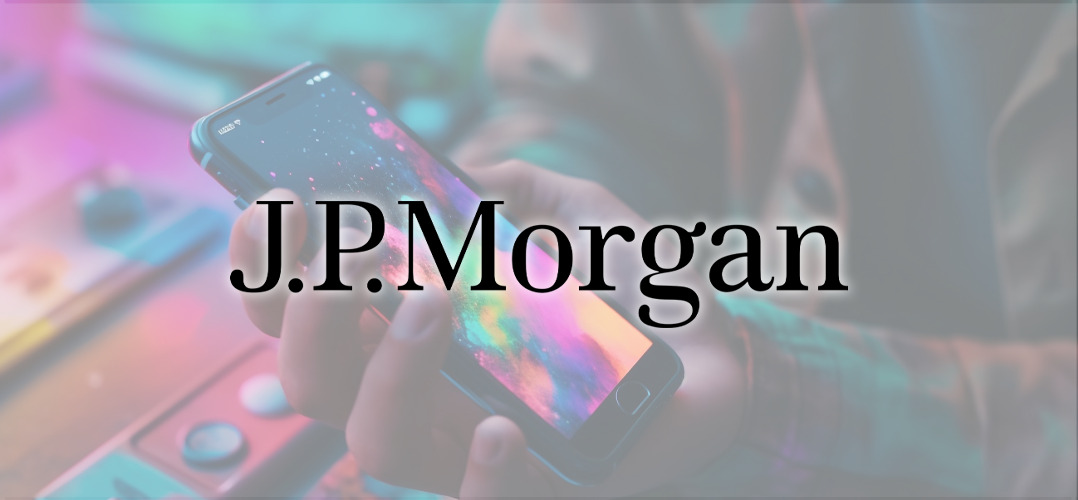
5.04%のグローバル包囲網
三拠点で動く資本
JPモルガンの戦略的布陣
2025年8月5日、関東財務局に提出された一通の大量保有報告書。その提出者は、JPモルガン証券グループの3法人
-
JPモルガン証券株式会社(日本法人)
-
J.P. Morgan Securities plc(英国法人)
-
J.P. Morgan Securities LLC(米国法人)
の連名による報告である。
彼らが保有するのは、KLab株式会社(3656)の発行済株式の5.04%に相当する3,040,881株。その内訳は以下の通り。
| 提出者法人名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|
| JPモルガン証券(東京) | 770,042株 | 1.28% |
| J.P. Morgan Securities plc(ロンドン) | 1,994,939株 | 3.30% |
| J.P. Morgan Securities LLC(ニューヨーク) | 275,900株 | 0.46% |
保有の本質
トレーディングとレンディングの“交錯”
提出書類によると、保有目的は以下の通り。
-
日本法人:証券業務としての投資目的
-
英国法人:証券・銀行業務としての保有
-
米国法人:トレーディング活動の一部
つまりこれは、「経営関与を目的としない資本」である。ただし、報告書の奥には金融機関ならではのリスクヘッジと流動性供給の機能が色濃く見える。
消費貸借契約・プライムブローカレッジの存在
- JPモルガン証券株式会社は803,432株をJ.P. Morgan Securities plcへ貸付
-
英国法人および米国法人は合計で約66万株以上を他の機関投資家へ貸付済み
-
特定機関向けの「空売り供給源」や「レバレッジ取引の資金源」として機能
これらの構造は、表面的には“所有”でありながら、実質的には“貸借・流動性確保のための在庫”である。
つまりJPモルガンはKLab株を流通市場で「裏から支える立場」にいるのだ。
なぜKLabなのか
割安放置銘柄としての吸引力
KLab株式会社は、スマートフォン向けゲームアプリを主力とする中堅ゲーム企業であり、近年はブロックチェーンゲーム・IP提携等で再起を図っている。
2024年度以降の特徴は以下の通り。
-
PBR:0.9倍前後(解散価値以下)
-
直近の赤字幅は縮小傾向、営業CFは黒字化達成
-
自己資本比率:約75%と健全
-
資産に比して株価が割安な水準で横ばい推移
つまり、企業価値の「割安感」が強く、市場内での取引が活発化しやすい“機関投資家向けの流動性ターゲット銘柄”となっていた。
このような銘柄は、JPモルガンのようなグローバル証券業者が“保有して貸す”という戦略でキャッシュフローを回収するための典型的な素材である。
5.04%という絶妙な構造
報告義務と規制逃れの境界線
保有比率の5.04%という数字にも注目したい。これは以下の意味を持つ。
-
5%超で大量保有報告書の提出義務発生(済)
-
10%未満では議決権行使やTOB義務が発生しない
-
報告義務は果たしつつ、経営関与の意図を回避できる水準
また、信用取引残高や貸借状況にも目配りすることで、市場での流動性を左右するインフラ的立場を得ている。
つまりこの5%は、「発言するための株式」ではなく、「市場構造を支配するための株式」である。
構造的プレゼンス
資本ではなく流通を支配するJPモルガンの構え
今回の大量保有報告は、アクティビストによる経営介入ではない。だが、それよりも深く市場構造に食い込む“流動性支配型資本”の典型事例である。
JPモルガンは、KLabの経営には口を出さない。だが、市場での売買の背後には必ず彼らの株式がある。
-
経営統治ではなく、取引統治(トレードガバナンス)
-
発言ではなく、流動性供給による“影の支配”
-
合法かつ透明なルートを使った超然としたプレゼンス
日本市場において、こうした“影の株主構造”をどれだけの個人投資家が意識できているだろうか?
「あなたの売買の裏に、彼らがいる。」
それが、今のKLab市場の実態なのである。

















