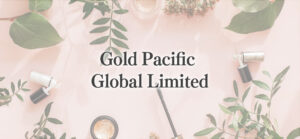Evo Fund×リミックスポイント「制度支配のスキームと過去資本政策の影」
過去の資本政策が生んだ“受け入れ体質”
リミックスポイントの調達履歴と制度的緩み
リミックスポイント(3825)は、再生可能エネルギーと仮想通貨という成長分野を掲げつつも、その資本政策は長年「希薄化ありき」で組まれてきた。
過去10年の中で、同社は幾度となく新株予約権・第三者割当増資・転換社債(CB)などを活用しており、そのたびに市場との信頼関係を試す結果となっている。
特に注目すべきは以下のような資本調達の履歴である。
-
2016年〜2020年:複数回にわたりMSワラント型資金調達を実施
-
2022年以降:仮想通貨事業拡大と金融関連M&Aを背景に増資を複数回断行
-
希薄化率が一時20%超を超える事例もあり、株価は断続的に乱高下
-
自社株買いや業績回復による株価支援施策は限定的
つまり、「割安な資本提供を受け入れる体質」が徐々に制度化されていたという構造が浮き彫りになる。そこに現れたのが、**Evo Fundによる“支配的スキーム”**だった。
Evo Fundの設計
“0.48円×5500万株”の構造と行使制限
2025年7月25日、Evo Fundはリミックスポイントと「第25回新株予約権に関する契約」を締結。この契約の中核は以下の構造である 。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新株予約権数 | 5,500万株分(発行済の約40%に相当) |
| 行使価格 | 0.48円(株価に比して数十分の1) |
| 行使制限 | 企業側の書面同意がなければ一定株数以上の行使は不可 |
| 譲渡制限 | 取締役会の事前同意なく他者への譲渡不可 |
| 借株含む保有比率 | 合計29.16%(うち借株 約148万株) |
制度の隙間を突く“合法支配”
なぜ違法でないのか?
第三者割当による資本政策は、法的には以下の条件で認められている。
-
株主総会の特別決議は不要(取締役会決議のみで可)
-
行使価格に対する下限規制は存在しない(東証の形式基準に従えばOK)
-
希薄化についても「30%超えであれば理由説明義務が発生」するだけで禁止ではない
つまり、「0.48円」という市場から大きく乖離した割当価格ですら、形式を整えれば合法となる。
また、行使制限や譲渡制限の設計は“支配はするが責任は取らない”ための防御壁でもある。
このような構造を、「制度の盲点を突いた」と断じるべきなのか、それとも「資本政策の柔軟性を活かした」と称賛すべきなのか──その評価は、企業の将来対応に委ねられている。
市場への影響と今後のリスク
Evo Fundの支配的構造は、リミックスポイントに複数の市場リスクをもたらす。
-
需給構造の変動リスク:予約権行使→売却が続けば、株価の下支えは困難に
-
経営の独立性への疑念:Evo Fundが発言力を持ち始めれば、企業の意思決定の透明性に影
-
個人投資家の評価低下:過去のMSワラント同様、“外資のための市場”という評価に
また、借株元であるBNPパリバやステートストリート銀行などの存在は、ファンド自身の流動性戦略が組み込まれている可能性を示唆する。
この支配は“制度の裏返し”
企業と制度、どちらが変わるべきか
Evo Fundによるリミックスポイントへの関与は、日本の株式市場に潜む“合法的であるが非倫理的”な構造の典型例だ。
-
資金調達に困窮する企業
-
フルに制度を読み解くファンド
-
形式を重視する東京証券取引所と金融庁
これらが交錯する中で、「29.16%の沈黙の支配者」が生まれた。
そしてこの問いが残る。
この構造を許容したのは企業か、制度か。それとも、我々投資家自身なのか。