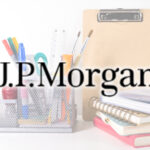オアシスマネジメントとは?
制度で企業を動かすファンドの哲学
オアシスマネジメント・カンパニー(Oasis Management Company Ltd.)は、2002年にセス・フィッシャー氏が香港で設立したアクティビストファンドである。
彼の経歴は米・タイガー・マネジメントやハイランド・キャピタルでの運用経験に裏付けられ、設立当初からアジア市場、特に日本・韓国に対する制度内アクティビズムを重視してきた。
このファンドは、保有比率が5〜10%の範囲に収まる範囲で株主提案、ガバナンス要求、配当戦略の見直しを合法的に行う“制度内型アクティビスト”の典型例である。
過去には以下のような実績がある。
- レオパレス21:外部取締役提案、資産売却、ガバナンス改革提案
- アトラHD:役員報酬の可視化と事業見直し
- JVCケンウッド:コーポレートガバナンス改革を巡る株主提案
- 東芝機械(現・芝浦機械):2020年、買収防衛策撤回に成功
この「買収はせずに、制度内で企業構造を変える」戦略こそが、オアシスの本質であり、今回の芝浦機械への再登場にも一貫している。
5.23%、制度限界まで接近した“布石の保有”
2025年8月22日、オアシスマネジメントが提出した大量保有報告書によると、芝浦機械に対する保有比率は5.23%(1,297,500株)に達した。
取得単価は3,915円で、合計投資額は約4.5億円程度に相当する。
ここで重要なのは「重要提案行為を行う可能性がある」という明記である。これは以下の意味を持つ。
- 株主提案権の行使(会社法303条)
- 取締役選任・解任議案の提出
- 配当政策、資本効率向上、ROE・ROIC指標の導入提案
この「いつでも動けるが、今は構えにとどめる」という戦略は、オアシスが他銘柄で使ってきた通称“沈黙の圧力”モデルと合致する。
芝浦機械の“改善未了領域”
なぜ再び狙われたのか
オアシスが芝浦機械に再び乗り込んできた背景には、経営指標や株主還元戦略に対する停滞感がある。
主な論点は以下の通り。
| 指標 | 現状 | 課題 |
|---|---|---|
| PBR | 約0.9倍 | 資産価値割れ、資本効率への市場不信 |
| ROE | 約6%前後 | 自己資本の活用効率が業界平均を下回る |
| 配当性向 | 約20〜25% | 明確な数値方針なし。自社株買いも不定期 |
| ガバナンス | 社外取締役導入済 | だが実効性と委員会運営の情報は限定的 |
ガバナンス改革の“体裁”はあるが、資本市場との対話姿勢が不足していることが、再度の「監視強化」に繋がった。
2026年株主総会に向けて
オアシスの次のシナリオ
今回の5.23%取得は、2026年3月期の株主総会に向けた布石と見るべきだ。
仮に芝浦機械側が現状のガバナンス・資本政策を維持し続けた場合、オアシスが次に取る可能性のある“提案行動”は以下の通り。
- 取締役選任案:外部経営陣による透明性強化
- ROEまたはROIC目標の導入提案
- 自社株買いの金額目標設定(例:年間50億円)
- 株主還元方針のKPI化(配当性向40%目標など)
また、こうした提案を通じて他の国内外機関投資家の“沈黙の賛同”を呼び起こす構造こそ、オアシスの真の影響力である。
「変わらなければ、再び問われる」
株主資本主義の第二幕へ
オアシスマネジメントは、芝浦機械にとって単なる投資家ではない。
それは、「かつて制度の力で経営の選択を変えさせた当事者」であり、今回もまた“経営陣が変わる意思を持てるか”という問いを沈黙のうちに発している存在である。
これは「再登場」ではない。これは「評価の継続」なのだ。
芝浦機械が今後自ら動くか、再び外圧によって動かされるか──その答えは2026年の総会、そしてその準備の中に現れてくる。