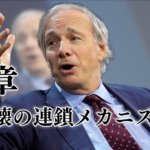制度の隙間を突く巨大外資の静かな支配力
ジャフコとゴールドマン
古くて新しい資本関係の再浮上
東証プライム上場の**ジャフコ グループ株式会社(8595)は、国内屈指の独立系ベンチャーキャピタルであり、旧野村證券系のDNAを引き継ぐ“日本型VC”の象徴的存在である。
このジャフコに対し、ゴールドマン・サックス証券とその海外関連会社群が合計で5.07%の株式を保有していることが、2025年8月22日に提出された報告書で明らかとなった。
報告形式は金融商品取引法第27条の26に基づく「特例対象株券等報告書」。
これは、一般的な大量保有報告とは異なり、「短期保有」「取引的目的」に限り開示義務が軽減される制度であり、本質的な保有意図や議決権行使のスタンスが“霧の中”に置かれることが多い。
報告内容のポイント
5社が連名で提出、実質は分散型支配
今回の提出者には、以下の5社が含まれる。
| 提出者名 | 保有株数 | 保有割合(%) |
|---|---|---|
| ゴールドマン・サックス証券(東京) | 2,600株 | 0.00%(控除後) |
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル(英国) | 2,425,545株 | 4.33% |
| ゴールドマン・サックス&Co. LLC(米国) | -101株 | 0.00%(控除超過) |
| GSアセット・マネジメント L.P.(米国) | 332,768株 | 0.59% |
| GSアセット・マネジメント・インターナショナル(英国) | 81,500株 | 0.15% |
| 合計 | 2,842,312株 | 5.07% |
保有目的は一貫して「有価証券業務上のトレーディングおよび借入・貸付」であり、いずれも純投資・運用を名目とした保有だが、その内訳はかなりテクニカルである。
注目すべきは、株式の一部が他のGSグループ間で貸借契約により動いており、金融商品の流動化・裁定取引の構造が内在していることだ。
実際、全体で3.6百万株相当を保有しながら、約118万株を控除する構造(貸借等)を取ることで、「実質的支配の影響力」は行使せず、制度上は“消している”と見ることができる。
ゴールドマンが狙うのは「議決権」ではない
変動利得と流動性管理の戦略構造
今回の報告書から読み取れるのは、以下のようなゴールドマン・サックスの典型的な運用構造だ。
-
議決権を行使しない「非アクティビスト型」保有
-
株券の貸借による両建て収益(貸株料+裁定取引)
-
短期保有+特例報告により“透明性を下げる”制度運用
つまり、「表に出ず、議決権を行使せず、利益だけは最大化する」という、大型外資の典型的な“金融エンジニアリング型戦略”と位置づけられる。
なぜジャフコだったのか
低PBR銘柄×安定収益モデルの妙味
ジャフコのような企業は、以下のような理由でゴールドマンにとって「極めて都合が良い」ターゲットになりやすい。
| 指標・構造 | コメント |
|---|---|
| PBR(株価純資産倍率) | 約0.7倍(2025年8月時点)と割安放置状態 |
| 流通株比率 | 自己株買い後も浮動株は一定量あり、貸借可能性高い |
| 事業特性 | 大型VC案件の売却益で期中に利益跳ね上がる構造 |
| IR活動の慎重姿勢 | アクティビスト対応が強くない |
ゴールドマンにとっては、「価格変動性が読める」「割安だが議決権圧力をかけずに利鞘を取れる」銘柄として、ジャフコは極めて合理的な“ターゲット”である。
制度の裏側で“透明に支配する”ゴールドマンの現在地
一見すると、ジャフコに対するゴールドマンの報告は静かなものだ。
だが、制度上は保有が認められ、かつ実質的影響力が見えない設計になっている点において、むしろ“支配的構造”の巧妙さが際立つ。
「ゴールドマンは支配しない。だが市場をコントロールする」
これは、アクティビストのように正面から衝突するのではなく、“制度内の透明な支配”を成立させるモデルであり、日本の資本市場のガバナンスと制度的透明性が、いかにグローバル戦略に利用され得るかを浮き彫りにしている。