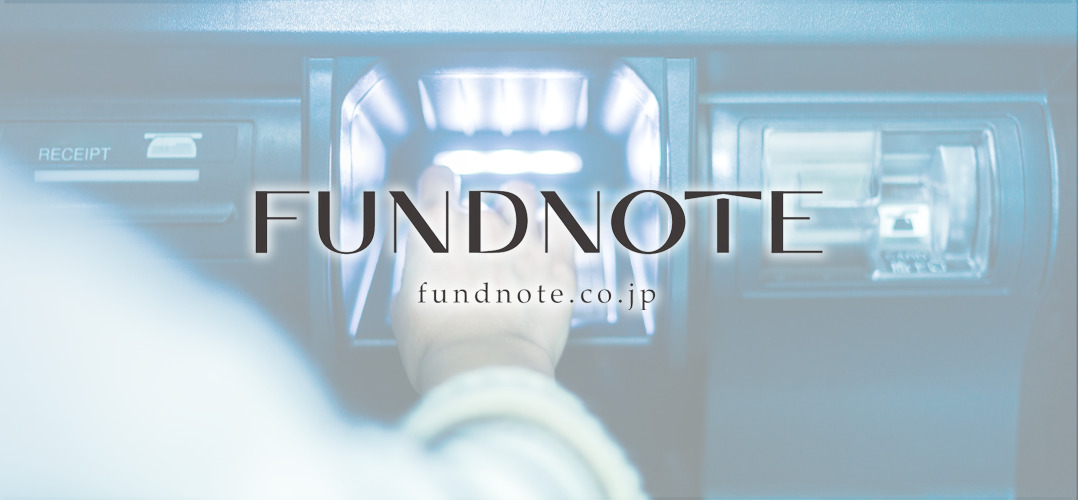
「地方銀行×アクティブESG運用」の新潮流
報告書の概要
2025年10月7日、fundnote株式会社(代表取締役社長:渡辺克真)が、大垣共立銀行(証券コード8361、東証プライム)の株式を5.39%保有していることが明らかになった。
報告義務発生日は9月30日。保有株式数は2,253,800株であり、提出書類は「大量保有報告書(特例)」の形式で関東財務局に提出された。
保有目的には、
「投資信託の信託財産の運用のため保有。スチュワードシップ・コードに則り、建設的な対話を通じてIR・資本効率・ガバナンスの高度化を促す」
と明記されている。
つまり、短期売買ではなく中長期的な対話型投資(アクティブ・オーナーシップ)が主目的であり、ESG運用や地域金融の再評価を背景とした資本参入とみられる。
fundnoteとは?
fundnote株式会社は2021年8月設立、本社を東京都港区芝に置く金融スタートアップ。
投資運用業および第二種金融商品取引業の登録を有し、新しい形の「ミドルリスク・ミドルリターン型」運用会社として注目されている。
代表の渡辺克真氏は国内外の資産運用業界出身で、機関投資家のスチュワードシップ活動や企業IR改革に精通した人物だ。
同社は、
-
企業対話を重視したESG運用
-
地方銀行・中堅企業を対象としたアクティブ投資
-
データドリブンによる企業価値評価モデル
を軸に、伝統的なファンドマネジメントとは異なるアプローチを展開している。
取得構造と運用体制
今回の大垣共立銀行株の保有は、投資助言会社Kaihou(カイホウ)の助言に基づいて運用する投資信託の信託財産として取得されたものである。
つまり、fundnote自身が直接株式を買い付けるのではなく、運用を助言型で実行する仕組みだ。
報告書には、「必要に応じて保有目的を“重要提案行為を行う”に変更する可能性がある」と明記されており、場合によっては経営提案・議決権行使を通じて企業変革を促す立場に転じる意図も読み取れる。
スチュワードシップ・コード準拠を明言している点も、国内機関投資家の中で際立つ特徴だ。
地方銀行への“建設的資本”として
大垣共立銀行は岐阜県を本拠とする地方銀行で、戦後の地域経済を支えてきた老舗金融機関である。
近年はフィンテックやキャッシュレスなど新しい領域への展開を模索しているが、地方銀行全体としては低金利・人口減少・収益構造の硬直化という課題を抱えている。
こうした中で、fundnoteのようなESG志向の運用会社が5%超の持分を保有することは、
-
経営の資本効率改善に対する外部刺激
-
企業価値向上を目的とした対話促進
-
地域金融機関へのESGマネー流入の端緒
として象徴的である。
fundnoteは「投資先企業と対話しながら、持続可能なリターンを共創する」ことを掲げており、これまでの投資ファンドが重視してきた「株価利益」ではなく、経営プロセスそのものの変革に焦点を置く。
視点と論点
-
“地方銀行”へのアクティブESGの波
東京中心の機関投資が、地域経済の再構築を視野に地方金融へ広がっている。fundnoteはその先駆けといえる。 -
対話型資本の新時代
「株主=敵」という構図を超え、資本が経営改善を伴走する関係へ。fundnoteは“伴走型投資”を実践している。 -
スチュワードシップ・コードの深化
単なる形式的遵守ではなく、地方銀行におけるESGとガバナンスの再設計を促す実働的プレイヤーが登場した意義は大きい。
“対話する資本”が地方金融を変える
fundnoteによる大垣共立銀行株の5.39%保有は、数字以上の意味を持つ。
それは、地方金融機関が外部資本と建設的な対話を通じて進化する時代の幕開けを告げるものだ。
投資とは、単なる株価の上昇を待つことではなく、企業と共に価値をつくること──。
fundnoteの動きは、アクティビストでもなく、従来型の運用機関でもない、“共創型アクティブキャピタル”の新しい形を体現している。
──金融の再生は、地方から始まる。

















