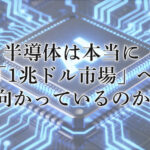“情報インフラ銘柄”を巡る外資の静かな動き
報告書が示す事実
2025年10月22日、ゴールドマン・サックス証券株式会社(代表取締役社長:居松秀浩)および関連会社ゴールドマン・サックス・インターナショナル(英国)が、株式会社アイネット(証券コード9600、東証プライム)株式の6.29%を共同保有していることが明らかになった。
報告義務発生日は10月15日で、保有株数は974,177株。
内訳は、
-
ゴールドマン・サックス証券株式会社:8,248株(0.05%)
-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル:965,929株(6.24%)
本件は自己勘定取引・ヘッジ取引を中心とした機関運用ポジションである
投資主体の構造
グローバル資本の分業体制
提出者の一つであるゴールドマン・サックス証券株式会社は、日本国内におけるゴールドマン・サックス・グループの中核。
虎ノ門ヒルズに本社を構え、金融商品取引業・M&A助言・自己勘定投資・デリバティブ取引を手掛ける。
一方のゴールドマン・サックス・インターナショナル(英国ロンドン)は、欧州・中東地域の資本運用およびトレーディング拠点であり、今回の報告では主要な保有主体。
同社は1988年設立、共同CEOはアンソニー・ガットマン氏とクナル・シャー氏で、欧州を代表する投資銀行兼マーケットメイカーとして知られる。
両社の関係は、証券会社とトレーディング本体の連携構造である。
今回の報告書でも、
-
ゴールドマン・サックス証券からインターナショナルへ411,300株の貸出
-
インターナショナルから証券側へ428,092株の貸出
という形で、相互に株券貸借(レンディング)契約が行われている
このような取引構造は、流動性確保・ヘッジ取引・裁定取引のいずれかを目的としたグローバル資本の典型的なポジション管理手法である。
対象企業アイネットとは何者か
株式会社アイネットは、データセンター運営、システム開発、クラウドソリューションを手掛ける情報インフラ企業。
1969年の設立以来、金融・製造・流通業界を中心にインフラ構築を担ってきた。
特に近年は、
-
「cloudstep」シリーズなどクラウド基盤事業の強化
-
金融向けデータセンターの拡張
-
AI・IoT連携サービスの実装
を通じて、企業DX支援の中核的プレイヤーとして存在感を高めている。
同社の時価総額は約500億円規模だが、ストック型収益構造を持つ安定成長企業として、海外ファンドからも注目度が高い。
ゴールドマンの狙い
流動性戦略とAIインフラ投資の伏線
今回の保有目的は「トレーディング業務」とされており、表向きは短期取引である。
しかし、注目すべきは同社がAI・データセンター・金融インフラといった「次世代ハードインフラ」を担う企業である点だ。
ゴールドマン・サックスは、グローバルではAI半導体やクラウド事業を含むインフラ関連セクターを戦略的ポートフォリオの中核に位置づけている。
日本市場においても、SMC、富士通、GMOクラウドなどと並ぶ情報・通信インフラ銘柄を重点投資対象にしており、
アイネット株の取得もAI時代の“日本型情報ベース”へのアクセスとしての意味を持つ可能性がある。
視点と論点
グローバル流動性の再配分
円安環境下で海外資本が再び日本株に流入する中、ゴールドマンは流動性供給者としての役割を果たしつつ、
日本市場の流動性を自社収益に転換する高度な戦略を展開している。
AI・クラウドの“インフラ裏銘柄”への注目
表向き地味なシステム企業ほど、AI時代のボトルネック(データ保全・演算処理)を握る。
アイネットのような企業は、海外マネーにとって“目に見えないテック資産”である。
外資の影響と日本市場の課題
海外機関投資家の短期取引が増えることで、株価変動リスクも高まる。
だが一方で、それは国内企業が国際資本市場の一部として再評価される機会でもある。
“トレーディングの裏側”に見える構造的潮流
ゴールドマン・サックスによるアイネット株6.29%の保有は、一見すると単なるトレーディング報告だ。
だが、その背後には、グローバル資本がAI・情報インフラ分野を新たな成長軸として日本市場に回帰しつつある潮流がある。
株券の貸し借りの奥に見えるのは、金融資本の静かな再配置である。
日本の情報インフラ企業は今、世界の資金地図の中で“静かに買われる資産”になっている。