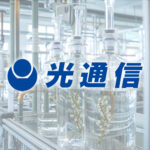【制度を突く“訂正型資本支配”】King Cho、GFA株式7.04%に修正
株式併合とCB行使の影で進行する“合法的継続支配”スキームの実態
2025年6月18日、香港を拠点とする外資系ファンド「景祥針織有限公司(King Cho Knitwear Company Limited、以下King Cho)」は、GFA株式会社(証券コード:8783)の大量保有報告書(変更報告書No.13)を訂正し、保有割合を従来報告の6.95%から7.04%へと修正した。
この数値自体はごく僅かな変動に見えるかもしれないが、実際には重大な構造的意義を孕んでいる──それは、株式併合後の発行済株式数を踏まえた“制度上の支配ラインの上抜け”であり、King Choが意図的に、あるいは制度を熟知した上で「報告義務発生回避」と「継続的な資本支配の正当化」を行っている可能性が濃厚である。
なぜ“訂正”に注目すべきか
❶ 表面上は誤記、実態は支配ラインの調整
King Choは過去1年間、CB(転換社債)と株式市場内取得を組み合わせた“回転的資本スキーム”をGFAに対して展開してきた。今回の訂正報告書では、「株式併合後の総数変動に伴う計算修正」という体裁を取っているが、実際には“議決権ベースの支配権維持・強化”という側面を含んでいる。
- 株式併合(2024年5月1日付:10株→1株)により表面上の株数は大幅減少
- しかし、CBの行使余地は減らず、希薄化可能性は温存
- それにもかかわらず、King Cho側は保有比率が「7.04%」であると訂正
→ つまりこれは、「株式併合によって相対的に議決権が高まった」ことを意味する。
❷ “報告義務該当事項なし”の記述が意味するもの
報告書の中で特に注目されるのが、「報告義務発生日:該当事項なし」という欄の存在である。7%を超える保有というのは、株主提案や議決権ベースの影響力において重要な意味を持つが、それにもかかわらずKing Choは「変更報告書の訂正のみで新たな報告義務は発生していない」と主張している。
この“法形式の裏をかく姿勢”こそが、希薄化スキームに通底するロジックである。
❸ CBスキームと訂正報告の連携が示す支配の持続性
King Choは、2024年以降GFAに対して断続的にCBを行使し、株式併合後も保有比率を調整しつつ市場での売却を繰り返している。これにより、
- 「議決権比率の最適点(6〜10%)」を維持
- 「新たな報告義務を避けながら」支配権を温存
- 「希薄化を前提に売却益を確定」するスキーム
が成り立っている。
今回の“訂正報告”は、こうしたスキームの「制度的持続可能性」の裏づけであり、単なる数値修正ではない。
GFAのIR姿勢と市場責任
問われるのは沈黙か、説明か
GFAはこれまで、King Choによる一連のCB行使と株式取得について、ほぼノーコメントを貫いてきた。
今回の訂正によって、GFAは以下の問いに対して明確な説明責任を問われることになる:
- 株式併合を実施したにもかかわらず、CBの行使枠はどう調整されたのか?
- 議決権ベースでの大株主となったKing Choの意向はどこまで経営に影響を与えるのか?
- 今後の資本政策は、既存株主利益をどこまで保護するものなのか?
これに応じなければ、市場は「説明なき資本支配」を容認することになり、企業価値そのものの信頼性が揺らぐことになる。
支配は静かに、しかし確実に進行する
King Choによる7.04%という保有比率訂正は、外形的には数値修正にすぎない。
しかしその内実は、株式併合という制度上の節目を利用した“議決権支配の温存”であり、既存制度の中で最大限に“報告義務回避”と“資本支配”を両立させた巧妙な戦略である。
投資家・アナリスト・ガバナンス関係者に求められるのは、「保有比率の上下に一喜一憂する」のではなく、その背景にある「制度利用の意図と目的」を読み解く構造的視点だ。
表面は“訂正”、その実態は“侵食”。今、GFAの資本構造が再び問われている。