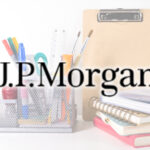モルスタグループ4社連携で“特例報告”の構造支配
FFRIセキュリティ
国産サイバー防衛の中核企業
FFRIセキュリティ(3692)は、国産セキュリティソリューションの草分けであり、サイバー空間の脅威から日本企業を守る数少ない“純粋国産”ベンダーである。
近年では政府調達、重要インフラ、IoT分野での実績が増え、国策・防衛銘柄としての注目度が上昇している。
そんなFFRIに、モルガン・スタンレー系4社が合計5.36%を保有していることが、2025年8月22日提出の大量保有報告書で明らかとなった。
報告書の構造
“連携支配”を可能にする特例スキーム
報告は、金融商品取引法第27条の26に基づく「特例対象株券等報告書」であり、通常よりも透明性が低い形での届出となっている。
| 提出者 | 保有数(株) | 保有割合(%) |
|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券(日本) | 340,978 | 4.16 |
| モルガン・スタンレー・インターナショナル(英国) | -10,400(控除) | -0.13 |
| モルガン・スタンレー・LLC(米国) | 108,622 | 1.33 |
| MS Equity Financing S.a.r.l.(ルクセンブルク) | 0 | 0.00 |
| 合計 | 439,200 | 5.36 |
複雑な貸借取引により、保有数の一部が控除されたり、ゼロになったりしている点が最大の特徴であり、実質的な株券の流動化と利益創出を意図した構造だと見られる。
「議決権を持たずして影響力を持つ」
金融エンジニアリングの実態
報告書では、各社が以下のように大量の貸借取引を行っていることが明記されている。
-
モルスタMUFGが機関投資家6名から約42万株借入
-
MS LLCが6.3万株借入/機関投資家に5.5万株貸付
-
MSインターナショナルが6.1万株借入+1.6万株貸付
これらは、「株主名簿に載らない形での支配」とも言える。
FFRIのような「国策」色の強い企業に対し、外資が“形式上の支配を避けつつ、流動性と情報を得る構造”を確立している様相が透けて見える。
なぜ今、FFRIなのか
割安・技術・テーマの三拍子
FFRIがターゲットとなった背景には以下の要素がある。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| バリュエーション | PBR 1倍以下で放置/黒字安定も成長期待低評価 |
| 市場テーマ | サイバーセキュリティ/政府調達/生成AIとの連携余地あり |
| 株主構成 | 浮動株率が高く、外資が流入しやすい構造 |
| IR活動 | 積極性がやや低く、“無風地帯”になりやすい |
モルガン・スタンレーは、これらの条件を満たすFFRIに対し「金融商品取引業の裁定対象」としてのポジションを取った可能性が高い。
「日本市場の穴」に住まう外資の“静かなる構造支配”
この報告書が象徴するのは、議決権や経営参加の意思は見せず、価格・需給・制度の隙間を縫って利得を得る“新たな支配のモデル”である。
ゴールドマン、バークレイズ、UBSと並び、モルスタもまた「特例報告」による“透明性回避型”の存在感を高めている。
FFRIのような技術系銘柄は、制度的な甘さと市場の油断が重なることで、「狙われやすいが気づかれにくい」という矛盾を抱えている。
今後も、こうした“静かな支配者たち”の動きを見逃さないためには、制度・報告書・貸借構造の読み解き力がますます重要になるだろう。