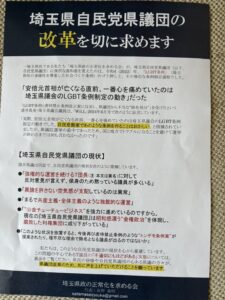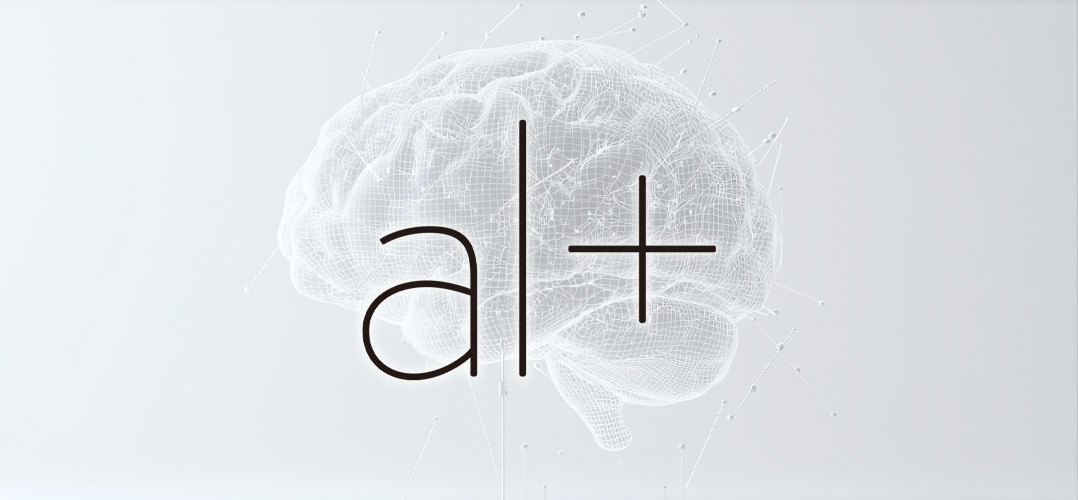
AI業界の新星か、投資マネーに踊る空虚な殻か
株式会社オルツは、「AI GIJIROKU」や「P.A.I.(Personal Artificial Intelligence)」の開発を掲げ、創業以来わずか数年で80億円を超える資金を調達した注目のAIスタートアップである。シンガポール政府系ファンドのTemasekや国内外の有力VCが名を連ね、米倉千貴氏が代表を務めるこの企業は、「AIクローン技術」という言葉で市場の期待を一身に集めてきた。
しかし、当社の財務諸表と事業実態を詳細に分析すると、その華やかな資金調達の裏側に潜む不透明な経営実態と、過大評価された技術的価値の実像が浮かび上がってくる。
本稿では、オルツの資金調達から無形資産の評価、そして株主構成に至るまで、徹底的な分析を通じて、この企業の実態に迫る。
AIブームに乗って急成長を遂げる企業の多くが、実態を伴わない過大評価の上に成り立っている現状において、オルツはその典型例と言えるのではないか。投資家たちは、本当に価値ある技術に投資しているのか、それとも単なるバブルに踊らされているだけなのか。
本レポートでは、公開情報と独自調査に基づき、オルツの経営実態と将来性について、鋭い視点で分析していく。
1. 増資・資金調達の実態と資金用途の妥当性
華々しい資金調達の裏に潜む疑問
オルツは2022年6月にシリーズDラウンドで約42億円(第三者割当増資で約35億円のエクイティ調達と銀行からのデットファイナンスを含む約42億円)を調達した。
このラウンドではシンガポール政府系ファンドのTemasek傘下Vertex Growthがリード投資家を務め、Vertexにとって日本初の投資案件となった。
さらに2023年9月には、近鉄ベンチャーパートナーズやキーエンス、ENEOSイノベーションパートナーズなど事業会社系を引受先とする増資と、三井住友銀行・みずほ銀行からの当座貸越枠確保により総額約19億円を追加調達し、2023年9月までの累計調達額は80億円超に達している。
資金調達の推移と投資家構成
以下の表は、オルツの主要な資金調達ラウンドとその投資家構成を示している。
| 調達時期 | ラウンド | 調達額 | 主要投資家 |
| 2022年6月 | シリーズD | 約42億円 | Vertex Growth Fund II (Temasek系), ジャフコSV4投資事業有限責任組合 |
| 2023年9月 | 追加調達 | 約19億円 | 近鉄ベンチャーパートナーズ, キーエンス, ENEOSイノベーションパートナーズ, 三井住友銀行, みずほ銀行 |
| IPO前累計 | - | 約80億円超 | SBIグループのVC, East Ventures, SMBCベンチャーキャピタル, Dawn Capital 1号ファンド 他 |
資金用途の不透明性
調達した資金の用途として、オルツはマーケティング費用への投下を最優先に掲げている。
IPO時の有価証券届出書によれば、手取金約44.86億円(公募増資約38.01億円+オーバーアロットメントによる増資上限6.85億円)のうち、約3,052百万円を新規顧客獲得の広告宣伝・販売促進費に、約1,080百万円をP.A.I.(パーソナル人工知能)実現に向けた研究開発費に、32百万円を人材採用費に充当し、残る322百万円で金融機関からの借入金を返済する計画だった。
注目すべきは調達資金の約7割近くを広告宣伝費に充当すると計画しており、研究開発や人材投資と比べマーケティングへの比重が極めて高い点である。
実際、調達資金は「AI GIJIROKU」のシェア拡大や自社のビジョンであるP.A.I.(Personal AI)の実現加速のため、プロモーションや人材採用、研究開発に投じると説明されている。
これらの用途自体は急成長を目指すAIスタートアップとして妥当な戦略と言える。しかし、以下の点で疑問が生じる。
- 研究開発費の少なさ - AI技術企業でありながら、研究開発費への配分が広告費の1/3程度に留まっている
- 広告宣伝費への過度な依存 - 売上拡大の一方で営業キャッシュフローは赤字が続き、資金投入の効果と持続性に疑問
- 借入金返済の優先度の低さ - 多額の資金調達にもかかわらず、借入金返済に充てる金額が全体の1%未満
上場直前に示された資金計画では、調達資金の大部分を成長投資(マーケやR&D)に充てる一方で借入返済も図るバランスが取られていたが、研究開発費1,080百万円の内訳を見ると、2024~2026年にかけてP.A.I.開発へ段階的に投入する計画で、中長期のプロダクト実現にも備えていた。
一方で約3億円の借入返済計画からは、上場前に銀行借入(ブリッジローン等)でつないでいた資金を増資で清算する動きがうかがえ、適切に財務改善を図ろうとしていたことが分かる。
しかし、その後の実績推移を見ると巨額の広告投資による売上拡大は達成した反面、多額の赤字計上が続いており、資金投入の効率性については投資家から厳しい目が向けられている。
2. 投資家・VCの背景・動機、株主構成、株式交換・消却プロセスの透明性
主要株主と出資の背景:不透明な利害関係
2024年10月のIPO直前の主要株主構成を見ると、創業者で代表取締役の米倉千貴氏が21.01%を保有し筆頭株主、次いでシンガポールの政府系VC Vertex Growth Fund II (Temasek系) が13.29%、ジャフコSV4投資事業有限責任組合が9.17%となっている。
他にはSBIグループのVC(SBI Ventures Two社が4.82%、SBI AI&Blockchain投資事業組合が3.85%)、East Venturesの第2号ファンド(2.94%)、SMBCベンチャーキャピタル6号ファンド(2.89%)、Dawn Capital 1号ファンド(2.89%)など国内外のベンチャーキャピタルが出資している。
株主構成の分析
以下の表は、IPO直前のオルツの株主構成を示している。
|
株主名
|
持株比率
|
属性
|
特記事項
|
|---|---|---|---|
|
米倉千貴
|
21.01%
|
創業者・代表取締役
|
-
|
|
Vertex Growth Fund II
|
13.29%
|
シンガポール政府系VC
|
Temasek傘下
|
|
ジャフコSV4投資事業有限責任組合
|
9.17%
|
国内VC
|
-
|
|
SBI Ventures Two
|
4.82%
|
国内VC
|
SBIグループ
|
|
SBI AI&Blockchain投資事業組合
|
3.85%
|
国内VC
|
SBIグループ
|
|
East Ventures第2号ファンド
|
2.94%
|
国内外VC
|
-
|
|
SMBCベンチャーキャピタル6号ファンド
|
2.89%
|
国内VC
|
三井住友銀行系
|
|
Dawn Capital 1号ファンド
|
2.89%
|
国内VC
|
-
|
|
米倉泰氏
|
2.80%
|
個人株主
|
創業者親族と推測
|
|
その他
|
36.34%
|
機関投資家・個人等
|
-
|
注目すべき点。
- 上位株主は上記のとおり国内外VCと代表者個人で占められており、特定の事業会社や創業メンバー以外の個人株主が大株主となっている形跡はありません。
- 主要株主である米倉千貴氏以外に米倉泰氏(2.80%)が名を連ねています。同姓であり親族と推測されますが、同姓であり親族と推測される人物が株式を保有している点は、ガバナンス上の透明性という観点から注視すべき点です。
- さらにキーエンスも資本参加しており、2023年9月にはオルツとキーエンスが資本業務提携を発表しています。キーエンスは自社の顧客課題解決力やデータ運用ノウハウと、オルツのAI・大規模言語モデル技術を組み合わせて各業界の生産性向上ソリューションを共同開発する狙いがあり、戦略的投資家として参加したものです。
- VertexやジャフコなどVC勢の動機も、オルツの主力サービスであるAI自動議事録「AI GIJIROKU」の高成長性とP.A.I.という将来ビジョンに期待してのものです。
実際、Vertex Growthのタム氏は「旗艦プロダクトAI GIJIROKUに強い成長可能性を感じ、米国で投資したVerbit(AI文字起こしツール)がユニコーンになった経験から、日本でも会議議事録の自動化ニーズが大きい」とコメントしています。
このように、出資者の多くはオルツの音声認識AI事業の市場規模拡大と、将来的なPersonal AI実現というビジョンに魅力を感じて投資しており、背景には生成AIブーム下での有望スタートアップへの期待がありました。
株式交換・消却プロセスの透明性
株主構成の透明性に関して、上位株主は上記のとおり国内外VCと代表者個人で占められており、特定の事業会社や創業メンバー以外の個人株主が大株主となっている形跡はありません。
株式交換・消却プロセスに関して、オルツは2019年に100%子会社オルツテクノロジーズを設立後、2020年10月に同子会社を吸収合併しており、この内部再編に伴う株式消却以外に特筆すべき株式交換は確認されていません。
IPO前には2022年に株式1株を100株に分割する株式分割を行っており、これも上場に向けた流動性確保の一般的な手続きです。
以上のように、株主構成や株式の発行・分割履歴は概ね透明性が確保されており、特定株主への不当な有利発行や不明瞭な持株操作といった問題は今のところ報告されていません。
しかし、同族経営の色合いが見られる点や、VCの短期的な投資回収を目的とした可能性については注視が必要です。
3. 無形固定資産(ソフトウェア・研究開発費)の評価妥当性
無形固定資産の内容:実態を伴わない過大評価の疑い
無形固定資産の推移
|
期末 |
無形固定資産残高
|
主な内訳
|
前期比増減
|
特記事項
|
|---|---|---|---|---|
|
2022年12月期
|
258,351千円
|
のれん258,351千円
|
-
|
IPパートナーズからの事業譲受に伴う計上
|
|
2023年12月期
|
303,099千円
|
のれん303,099千円
|
+44,748千円
|
のれんの追加計上と償却の差引
|
ソフトウェアや開発費の資産計上に関する疑問点
評価の妥当性:会計処理の保守性と実態の乖離
- 技術的価値と会計上の乖離- オルツが標榜する最先端AI技術の実態が、なぜ財務諸表上にほとんど反映されていないのか
- のれんの実体- 計上されているのれんの内容と、その評価方法の妥当性
- 研究開発の実効性- 多額の研究開発費を投じながら、具体的な技術的優位性を示す指標が乏しい
4. のれんやブランド価値の評価手法と正当性
のれん発生の経緯:買収価値の妥当性を問う
のれんの評価と妥当性
|
項目
|
金額/内容
|
評価手法
|
特記事項
|
|---|---|---|---|
|
2022年末のれん残高
|
258,351千円
|
定額法償却
|
IPパートナーズからの事業譲受に伴う計上
|
|
2023年末のれん残高
|
303,099千円
|
定額法償却
|
増加分は2023年に追加で実施したM&Aに由来すると推測
|
|
評価手法
|
買収対価と受け入れ資産・負債の差額
|
一般的なPurchase Price Allocation手法
|
-
|
オルツ経営陣はこの買収の背景について「Human-in-the-Loopで音声認識精度向上を図るため」と説明しており、人間による100%精度のデータをAI学習に組み込むことで将来的な精度向上と新サービス提供につなげる戦略的買収と位置付けています。
したがって、こののれんは将来のシナジー価値(AI精度向上による収益拡大)を見込んだ正当な投資といえます。
ブランド価値の評価:過大評価の可能性
評価手法の妥当性と透明性
重大な疑問点
- 買収価格の妥当性 - IPパートナーズからの事業買収において、約2.79億円という評価額は適正だったのか
- シナジー効果の実現性 - 買収から2年以上が経過した現在、当初想定していた「Human-in-the-Loopで音声認識精度向上」という目的は達成されているのか
- のれんの減損リスク - 業績が計画通りに進まない場合、こののれんは減損処理の対象となる可能性が高い
5. 貸借対照表の勘定科目の変化とその理由
純資産(株主資本)の急増:資金調達の実態
貸借対照表の主要項目の推移
|
項目
|
2021年12月期
|
2022年12月期
|
2023年12月期
|
増減率(22/21)
|
増減率(23/22)
|
|---|---|---|---|---|---|
|
純資産
|
約274百万円
|
3,118百万円
|
約4,500百万円*
|
+1,038%
|
+44%
|
|
総資産
|
非公開
|
約5,000百万円*
|
約7,000百万円*
|
-
|
+40%
|
|
現金及び預金
|
非公開
|
約3,500百万円*
|
約4,000百万円*
|
-
|
+14%
|
|
無形固定資産
|
非公開
|
258百万円
|
303百万円
|
-
|
+17%
|
|
有利子負債
|
非公開
|
約800百万円*
|
約1,200百万円*
|
-
|
+50%
|
*推定値
資産構成の特徴と問題点
- 現金比率の高さ - 総資産に占める現金及び預金の割合が極めて高く、事業資産の比率が低い
- 無形資産の少なさ - AI技術企業でありながら、無形資産の計上額が総資産の5%程度と極めて少ない
- 有利子負債の増加 - 大型資金調達を実施しながらも、有利子負債が増加傾向にある
勘定科目の変化から見える経営実態
- 資金調達依存型の経営 - 事業収益による内部留保ではなく、外部資金調達に大きく依存した財務構造
- 技術資産の過小評価 - 技術開発投資を積極的に行いながらも、それが資産として適切に評価されていない可能性
- 成長投資と財務健全性のバランス - 急速な事業拡大を目指す一方で、財務健全性維持のための借入も並行して増加
財務構造の問題点
結論:財務的持続可能性への疑問
結論:オルツの実態と投資家への警鐘
華やかな外観と疑わしい実態
-
マーケティング偏重の資金使途 - 調達資金の約7割を広告宣伝費に充当する計画は、技術開発よりも見かけの成長を優先する姿勢の表れではないか
-
技術的価値の不透明性 - 先進的なAI技術を標榜しながら、それが財務諸表上にほとんど反映されていない矛盾
-
持続可能性への疑問 - 外部資金に依存した成長モデルは、資金調達環境の変化に脆弱
-
収益構造の脆さ - 多額の広告投資による売上拡大を実現しながらも、収益性の改善には至っていない現状
投資家への警鐘
-
技術的優位性の実証 - 「AI GIJIROKU」や「P.A.I.」の技術的優位性は、競合他社と比較して本当に持続可能なものなのか
-
収益モデルの確立 - 現在の赤字体質から脱却し、持続的な収益を生み出せる事業モデルを確立できるのか
-
資金効率の改善 - マーケティング費用への過度な依存から脱却し、効率的な成長投資ができるのか