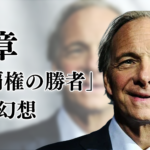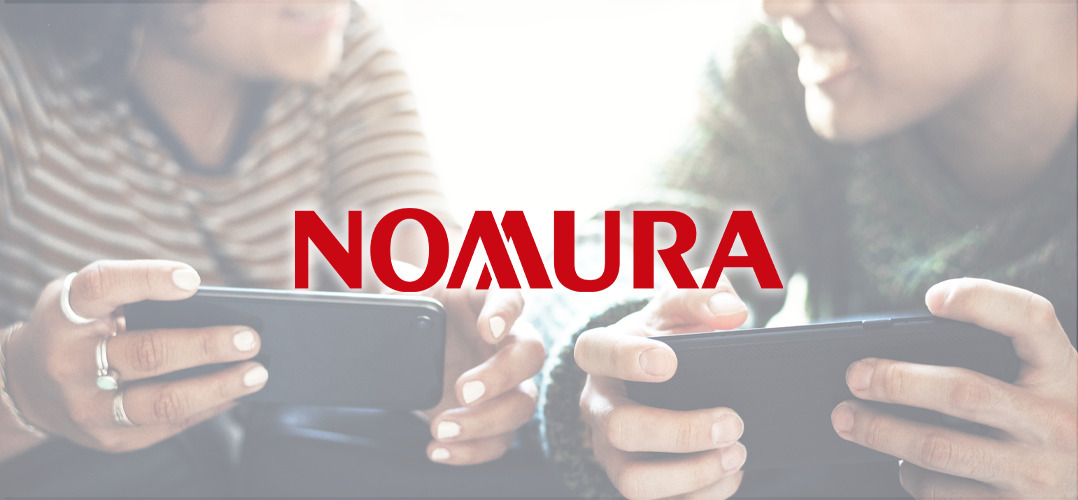
ゲーム業界における需給主導の力学
2025年9月19日、野村證券と野村アセットマネジメントは、KLab(3656・東証プライム)に関する大量保有報告書を提出した。報告義務発生日は9月15日。
両社の合計保有株数は 3,596,988株(発行済株式60,392,300株の5.96%)。
一見すると「大手機関投資家の参入」と捉えられがちだが、その内訳を見ると、証券会社在庫と信託財産の運用が絡み合う、典型的な需給主導型のポジションであることが浮き彫りになる。
KLabとは
波の荒い「IP依存型ゲーム開発企業」
KLabは2000年創業、スマホゲーム黎明期から参入してきた独立系開発会社。
-
代表タイトル:「BLEACH Brave Souls」、「ラブライブ!スクフェス」などアニメ・漫画IPを活用した作品群。
-
収益モデル:ヒットタイトルの運営課金収入に依存。
-
特徴:海外市場への展開にも積極的だが、国内IPへの依存度が依然として高い。
こうしたビジネスモデルは、一作ヒットすれば業績は急伸、失敗すれば急落という「振れ幅の大きい銘柄特性」を持つ。
そのため、株価は常に需給要因や市場テーマに敏感に反応し、投資家からは「材料株」としての色合いが強い。
野村證券のポジション
在庫としての3.63%
-
保有株数:2,191,088株(3.63%)
-
保有目的:「証券業務に係る商品在庫」
-
実態:ディーリング在庫として短期的に株式を抱え、顧客取引・貸株業務・ヘッジに利用。
さらに詳細を見ると、
-
野村アセットから25.5万株、SBI証券から170万株などを借入。
-
Nomura International plc(英国)へ約219万株を貸出。
つまり、実質的には在庫循環と貸株業務の中で発生している数字であり、長期投資家の安定保有とは全く性格が異なる。
野村アセットのポジション
信託財産としての2.33%
-
保有株数:1,405,900株(2.33%)
-
保有目的:「信託財産の運用」
-
実態:投資信託や年金資金を背景に保有しつつ、大部分を外資系証券に貸株。
具体的には、モルガン・スタンレーMUFG証券へ64万株、バークレイズ証券へ36万株、ソシエテ・ジェネラル証券へ5万株、シティグループ証券へ1,700株、ゴールドマン・サックス証券へ100株など、合計106万株超を貸出している。
ここから見えてくるのは、信託資産による安定保有の裏で、実際には株式が市場に再供給され、空売りや裁定取引に利用されている現実である。
投資家へのインプリケーション
今回の5.96%保有は「機関投資家がKLabに参入した」というよりも、株式需給の歪みを象徴する開示と解釈すべきだ。
プラス材料
-
名目上の大株主出現により、市場での注目度が上がる。
-
信託財産としての一部保有は中期的に資金流入を示唆する。
マイナス材料
-
実態は在庫・貸株が中心であり、需給主導で株価が乱高下するリスクが高い。
-
信託財産の多くが貸株として流通しており、空売り残高増加による株価下押し圧力にもつながる。
ゲーム業界の文脈
KLab再評価の芽はあるか
スマホゲーム業界は2020年代に入り、以下の転換点を迎えている。
-
IP競争の激化:人気アニメ・漫画IPの取り合いが激しい。
-
開発費の増大:大作は数十億円規模、外れれば大赤字。
-
グローバル化:中国・韓国勢との競争が激化。
こうした中で、KLabは「IP依存型の老舗」として再評価されにくい一方、新規IP獲得や海外展開が成功すれば株価の爆発力は大きい。
今回の野村グループの保有も、投資妙味というよりは「需給波乱の火種」として投資家の意識に残るだろう。
「5.96%」の意味をどう読むか
野村證券と野村アセットによるKLab株5.96%保有は、
-
表面的には大株主参入
-
実質的には証券在庫+貸株による需給操作的ポジション
という二重性を持つ。
投資家は、この数字を「長期信任票」ではなく「短期需給シグナル」として読み解く必要がある。
ゲーム株特有の材料感と絡み合えば、KLabの株価は再びボラティリティを増す可能性が高い。