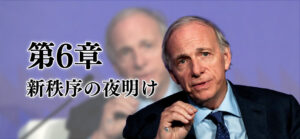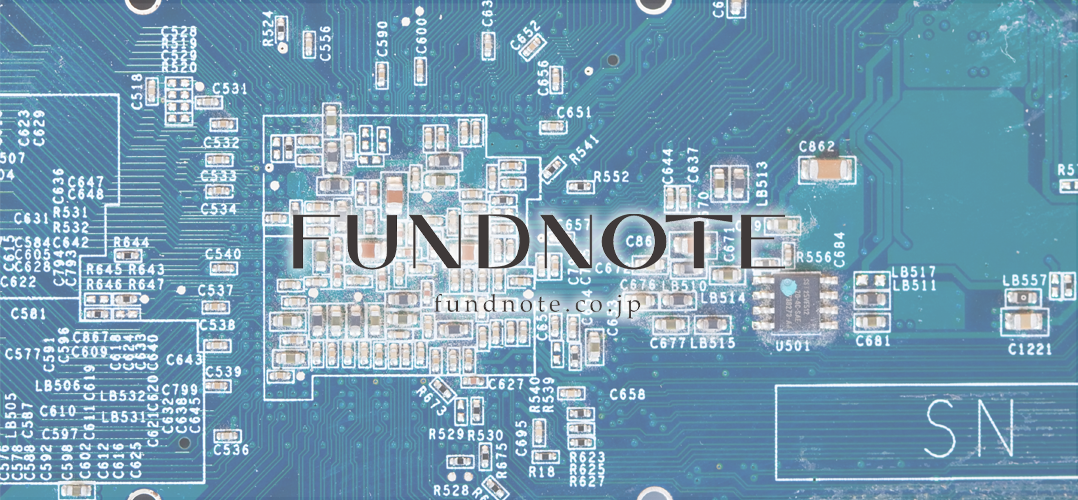
大量保有報告書の提出
国産アクティビストの台頭
2025年11月10日、fundnote株式会社が関東財務局に提出した大量保有報告書により、同社が日本シイエムケイ株式会社(東証プライム・6958)の株式を6.66%保有していることが明らかとなった。
報告義務発生日は2025年10月31日。
保有株数は4,744,200株、発行済株式総数71,256,476株に対する比率は6.66%に達する。
これにより、fundnoteは実質的に筆頭株主圏内へと浮上した格好となる。
本件は単なる保有開示にとどまらない。
注目すべきは、同社の「保有目的」欄に記された一文だ。
「スチュワードシップ・コードに則り建設的な対話により、IR・資本効率・ガバナンスの高度化と企業価値向上を促す。但し、受益者の利益を保全する為に、保有目的を『重要提案行為を行う』に変更する場合がある。」
fundnote株式会社とは
若いが鋭い投資運用業者
fundnote株式会社は、2021年8月26日に設立された新興の投資運用業者である。
本社は東京都港区芝5丁目のクロスオフィス三田に所在し、代表取締役社長は渡辺克真氏。
事業内容は、金融商品取引法に基づく投資運用業および第二種金融商品取引業。
fundnoteの特徴は、単なるアクティブ運用会社ではなく、「対話型資本運用」を軸にしたエンゲージメント・ファンドである点にある。
運用哲学の中心には、次の3本柱があるとされる。
-
ガバナンス改革への関与:取締役会の構成、独立性、報酬体系などへの提案
-
資本効率の改善:ROE・ROIC指標に基づく資本政策の是正要求
-
IR・情報開示の透明化:企業の説明責任を重視した対話促進
保有構造
本件の保有は、株式会社Kaihou(カイホウ)による投資助言に基づくものと明記されている。
fundnote自身が主体的に投資判断を行ったわけではなく、信託財産の運用目的で保有している構造だ。
しかし、ここにこそ本件の核心がある。
つまり、「助言者が戦略を握り、fundnoteが表層に立つ」二重構造である。
この形態は、国内で近年増加している「ファンド・オブ・ファンズ型アクティビズム」の特徴と一致する。
つまり、“受益者利益の保全”を名目に経営関与を拡張できる仕組みを内包しているのだ。
報告書に見るfundnoteの意図
fundnoteの報告書には「建設的な対話」という言葉が繰り返されている。
この表現は一見ソフトだが、実際には以下の三段階の行動余地を意味している。
-
IRへの改善要求(情報開示の強化・説明責任)
-
資本効率向上提案(自己株買い・配当政策の見直し)
-
経営ガバナンス提案(取締役構成・独立性の強化)
これらはいずれも、スチュワードシップ・コードにおける「建設的対話」の範疇に入るが、最終行には明確に「重要提案行為に変更する場合がある」と記されている。
すなわち、fundnoteはアクティビズム型の転換条項を正式に文書上で明言したことになる。
このような表現を使う投資運用会社は、国内でもまだ少数派である。
対象企業・日本シイエムケイの文脈
日本シイエムケイは、プリント配線板(PCB)の大手メーカーとして知られる。
自動車向けを中心にグローバル展開を進めるが、近年は原材料コスト上昇と中国景気減速の影響を受けて利益率が低下している。
また、直近ではROE・ROAともに10%を割り込み、
キャッシュリッチでありながら資本効率の低い企業として、機関投資家の改善要求対象に挙げられやすい構造を持つ。
fundnoteが同社を保有する理由を「資本効率・ガバナンス高度化の促進」としたのは、
この構造的な改善余地を狙った戦略的判断と見られる。
6.66%という“静かな臨界点”
保有比率6.66%──この数字には意味がある。
5%を超えると大量保有報告義務が発生し、10%を超えると安定株主としての影響が強まる。
その中間域である6〜7%は、「牽制可能な持分」と呼ばれるレンジだ。
この比率は、企業に「話し合いを避ける余地を与えない」一方で、
「支配的株主と見なされない」という絶妙なバランスを保つ。
つまり、圧力と合法性を両立する“黄金比”とも言える。
fundnoteはそのレンジを狙い撃ちした。
この数字の裏には、制度を理解した上での戦略的設計が見える。
スチュワードシップ・コードと新しい“国内アクティビスト”像
fundnoteが掲げるスチュワードシップ・コード遵守の姿勢は、
従来の外資系アクティビストとは異なる。
彼らは「対立」ではなく、「関与」を選ぶ。
この流れは、機関投資家が企業と建設的に対話し、
長期的な企業価値向上を促すというESG時代のアクティビズムである。
しかし、その実態は「形式的対話から実質的経営関与へ」の布石である。
fundnoteの報告文言はまさにその過渡期を象徴する。
“見えないアクティビズム”の進行
今回の大量保有報告は、単なる法令遵守の書類ではない。
そこには、日本市場における「新しい株主行動主義の波」が刻まれている。
外資ではなく、国内の新興投資運用会社が、
スチュワードシップ・コードを盾に、資本政策の議論に踏み込もうとしている。
これは、かつての村上ファンド型の強硬手法ではなく、
ESG・ガバナンスの言語をまとった“知的アクティビズム”だ。
企業統治改革の次のステージは、
外資ではなく、国内から生まれる可能性が高い。
fundnoteはその象徴的な存在になりつつある。
「提案行為」に踏み出す日
今後、fundnoteが「重要提案行為」に踏み込む日が来れば、
それは国内アクティビズム第2幕の開幕を意味するだろう。
同社が指摘する「IR」「資本効率」「ガバナンス」は、
いずれも日本企業が長年抱えてきた構造的課題である。
fundnoteが静かに動くその先に、
“対話の名を借りた改革圧力”が待っている。