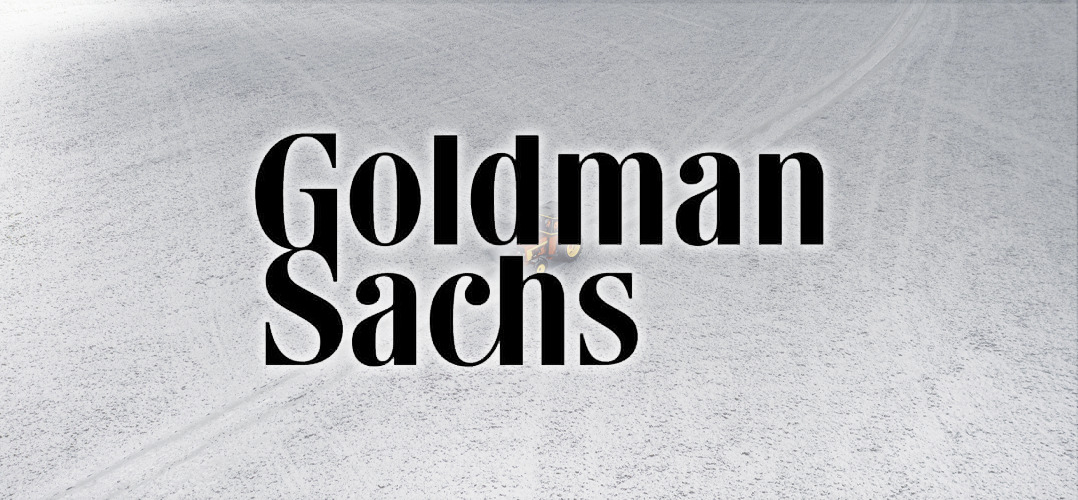
グローバル資本が狙う「日本の基礎素材」
第1章 報告書が示す事実
2025年10月22日、ゴールドマン・サックス証券株式会社(代表取締役社長:居松秀浩)およびその関連会社5社が、太平洋セメント株式会社(証券コード5233、東証プライム上場)株式の5.61%を共同で保有していることが明らかになった。
報告義務発生日は10月15日で、総保有株数は6,634,521株。
主な構成は以下の通り
-
ゴールドマン・サックス証券株式会社(日本): -1,600株(0.00%)
-
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(英国):4,728,265株(4.00%)
-
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC(米国):8,507株(0.01%)
-
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントL.P.(米国):1,543,828株(1.31%)
-
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(英国):355,521株(0.30%)
このように、米・英・日を横断したグローバルな資本連携体制での保有構造となっている。
取引の性格
“トレーディング”と“長期運用”の二面性
報告書上の保有目的は「有価証券関連業務の一部としてのトレーディングおよび有価証券の借入等」と記載されており、一見すると短期的な裁定取引に見える。
しかし、内訳を精査すると、アセットマネジメント部門による長期運用型の保有が全体の約3割を占めている。
特に、Goldman Sachs Asset Management(GSAM)が運用する米英両部門(L.P.およびInternational)による保有は1.9%以上。
これは単なる流動性取引ではなく、投資信託・年金資金を通じたESG・インフラ関連投資の一環であることを示唆している。
太平洋セメントの企業構造と投資魅力
太平洋セメントは、国内セメント最大手。旧秩父セメント、旭セメントなどの系譜を引き、
-
セメント・コンクリートなどインフラ基礎資材の供給
-
再生資源・廃棄物処理
-
地熱・再エネ発電などの環境ソリューション
を中核に据える“総合素材企業”である。
2024年以降、建設需要の回復や公共インフラ投資の拡大、さらには再エネインフラへの参入を背景に業績が上向いており、株式市場では「環境対応型セメント企業」として再評価の兆しが出ている。
ゴールドマンによる5.61%の保有は、こうした構造変化を踏まえた素材×サステナビリティ領域への資本介入として注目される。
保有構造の実態
株券貸借ネットワーク
報告書によれば、ゴールドマン各社の間では大規模な株券の貸借(レンディング)契約が行われている。
-
日本法人から英国法人への貸出:688,571株
-
米国法人からの借入:140,661株
-
欧州銀行(Goldman Sachs Bank Europe SE)からの借入:193株
-
さらに、投資家向けには150,520株を機関投資家から借入
このように、同一グループ内外で複数方向の株券貸借が発生しており、流動性確保とヘッジ運用を目的とした複層的ポジション構造となっている。
同社が“トレーディング”と“運用”を併用していることを裏付けるデータだ。
グローバル資本が見る「素材産業の未来」
ゴールドマン・サックスが太平洋セメントを保有する背景には、「脱炭素×インフラ更新」という世界的テーマがある。
セメント産業は二酸化炭素排出量の大きい分野であるが、同時に再生社会の根幹を支える不可欠な産業でもある。
太平洋セメントは既に「カーボンニュートラル2050戦略」を公表しており、
-
廃棄物燃料(RDF・RPF)の使用拡大
-
カーボンキャプチャー技術の実装
-
リサイクル骨材による循環型コンクリート開発
など、脱炭素ソリューションを多面的に展開している。
これらの動きは、ESG投資基準を重視する欧米機関投資家の評価軸に合致しており、ゴールドマンの保有も「短期売買ではなく、構造的リスクを織り込んだ長期リターン」を狙う戦略とみられる。
視点と論点
素材産業における“脱炭素プレミアム”
かつて環境負荷産業とみなされてきたセメント業界に、ESGマネーが流入し始めている。
ゴールドマンの投資はその先駆けといえる。
トレーディング部門と資産運用部門の協調
同一グループ内で短期・中期・長期資本を自在に組み合わせることで、リスクを最小化。
日本市場でもこの“統合運用モデル”が拡大する兆しがある。
外資資本の“地方製造業再評価”
太平洋セメントの主要拠点は群馬・秩父など地方圏。
外資マネーが地方製造拠点を評価し始めたことは、日本の産業地図の地殻変動を意味する。
静かに買われる“社会インフラ銘柄”
ゴールドマン・サックスによる太平洋セメント株5.61%保有は、単なる流動性取引にとどまらない。
それは、「環境×インフラ」という新しい投資テーマにおける日本企業の再評価の象徴である。
セメントは、建設と再生の両方をつなぐ社会の土台だ。
グローバル資本は今、その“地味だが欠かせない企業群”を静かに拾い集めている。
株式市場の真の主役は、派手なAI銘柄ではなく、社会を支える素材企業なのかもしれない。

















