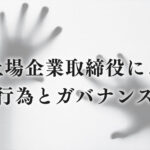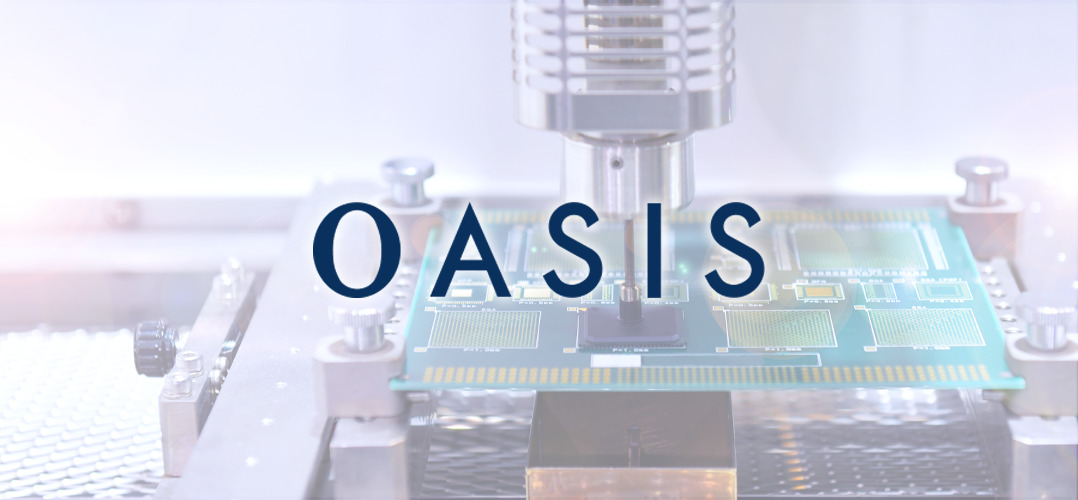
あの“買収防衛撤回”劇の主役、再び登場
オアシスマネジメントの因縁
2020年、芝浦機械(旧・東芝機械)は、アクティビストファンド「オアシスマネジメント」によって、日本のコーポレートガバナンス史に残る一大事件を経験した。
オアシスは当時、株主提案を駆使して買収防衛策の撤回を迫り、最終的に芝浦機械側が譲歩。日本で初めて、機関投資家による防衛策撤廃が実現した事例として市場に衝撃を与えた。
それから5年──同じファンドが再び動いた。
2025年8月、提出された最新の大量保有報告書によると、オアシスマネジメントが芝浦機械の5.23%(1,297,500株)を保有していることが判明。
しかも、保有目的欄には明確に「重要提案行為を行う可能性」が示されている。
報告書のポイント
提案権と監視力を確保した“最小支配”の設計
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保有比率 | 5.23% |
| 保有株数 | 1,297,500株 |
| 取得単価 | 3,915円(市場外取引) |
| 報告義務発生日 | 2025年8月19日 |
| 保有目的 | ポートフォリオ投資+重要提案行為 |
| 取得資金 | 約4.47億円(自己資金) |
この「5.23%」という保有比率は極めて象徴的である。というのも、
- 5%以上で株主提案権を制度的に行使可能(会社法303条)
- 10%未満で、TOB(公開買付)規制や主要株主規制を回避
つまり、最小限の投資で最大限の制度的影響力を確保した構造が明確に見て取れる。
さらに直近2ヶ月での取得は80,000株(0.32%)にとどまり、大量の市場外取得=静かに仕込んだ“戦略的包囲網”の可能性が高い。
なぜ再び芝浦機械なのか
PBR低迷、還元性低下、IRの停滞
現在の芝浦機械は、以下のような状況にある。
- PBR:約0.9倍前後で低迷
- 自己資本比率は高いが、資本効率は低位安定
- 配当性向が業界平均を下回り、還元強化の兆しが乏しい
- 自社株買いは断続的で、株価押上げ効果に乏しい
- IR活動が控えめで、エンゲージメントに対する開示も少ない
オアシスは、こうした“資本効率改善の余地が大きいが、現状維持のまま放置されている企業”を標的にしやすい。
特に、過去に買収防衛策で対立した相手に再接近するという点は、“改革未完の企業に対する第2ラウンド”と捉えるべきだ。
市場への圧力と次の一手
サイレントシグナルは発せられた
今回の報告書には、「今はまだ動かないが、条件が整えば即座に動ける」というファンドの強いメッセージが込められている。
その背景には
- 経営陣が株主価値向上に動かなければ、議案提案に踏み切る可能性
- IRに応じない場合、メディア戦略や株主連携を用いる“間接圧力”
- 他の機関投資家への“起爆剤”として、ガバナンス改革機運を高める起点にもなる
この5.23%は、「発言なき監視」ではなく、「発言予告付きの合法的圧力」なのである。
芝浦機械は再び問われている
ガバナンスとは「守る」ことか「応える」ことか
2020年の事件以来、芝浦機械は企業統治体制や資本政策の“安定化”に向けて一定の取り組みを行ってきた。
しかし、それが十分な成果につながっているかは疑問である。
今回のオアシス再登場は、それ自体が経営陣に対する“事前警告”であり、制度的な緊張関係が再び生まれた瞬間である。
経営の自由とは、株主に応える義務を放棄することではない。
オアシスが再び芝浦機械を“投資先”と定義した今、次に行動するのは経営陣の番だ。